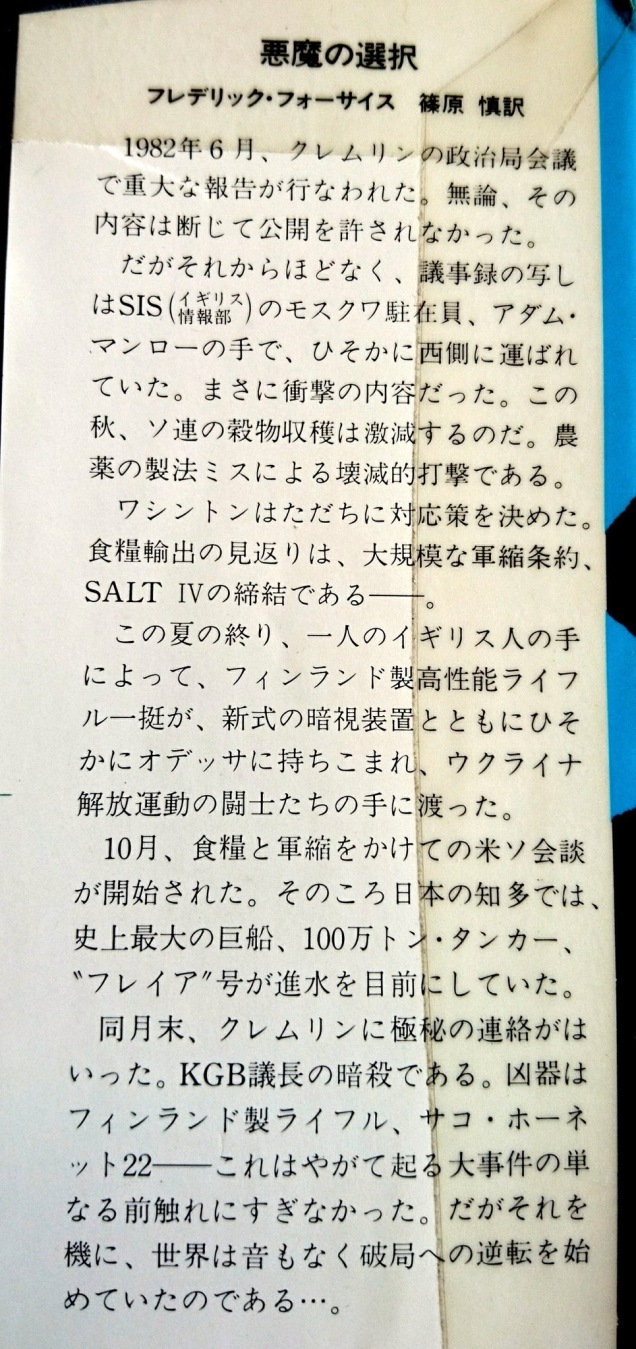◆はじめに
《ロシアの国家観においてイメージされる境界とは、★浸透膜のようなものだ。内部の液体(主権)は一定の凝集性を持つが、目に見えない微細な穴から外に向かって染み出してもいく。(中略)もしも外部の液体の方が浸透圧が高い場合、膜の内部には他国の「主権」がグラデーションを描きながら染み込んでくる。》(P14)
◆第1章 「ロシア」とはどこまでか―ソ連崩壊後のロシアをめぐる地政学
《現在のロシア国歌ではロシアを「愛しき我らの国」とするばかりで、国民団結の理念はやはり示されていない。(中略)この意味で、★現在のロシアにとって第二次世界大戦の記憶は貴重なアイデンティティのよすがとなっている。(中略)ソ連はここで全人類的な貢献を果たしたのだという自負は現在も極めて強い。(中略)ドイツの降伏を記念して毎年5月9日に行われる戦勝記念パレードは、そのことをまざまざと実感させてくれるイベントだ。》(P38~39) →★北方領土問題も「貴重なアイデンティティ」と直結している。サハリンでの戦勝記念パレードを想起。
《ソ連崩壊によって「ロシア的なるもの」は国境で分断され、新たに出現したロシアの国境内には「非ロシア的なもの」が抱え込まれることになった。つまり、★民族の分布と国境線が一致しなくなったわけで、こうなると「ロシア」とは一体どこまでを指すのか(国際的に承認された国境とは別に)という問題が生じてくる》(P42) →★ウクライナ紛争においても重要な点。
《大国志向的国家観においては、ロシアが旧ソ連諸国を帝国的秩序の下に直接統治することまでは想定しない。その一方で、★旧ソ連圏で生起する事象に関してロシアが強い影響力を発揮できる地位を持つべきであるという点では、大国志向は帝国志向との共通点を有する。》(P49)
◆第2章 「主権」と「勢力圏」―ロシアの秩序観
《(前略)たしかに歴史的つながりが深いとはいえ、れっきとした主権国家である旧ソ連諸国をロシアがこのように扱うことは、どのように正当化されるのだろうか。ひとことで言えば、★ロシアの考える「主権」とは、ごく一部の大国のみが保持しうるものだという考え方がその背景に指摘できよう。(中略)他国に依存せず、「自由」=自己決定権を自らの力で保持できる国だけがプーチン大統領の言う「主権国家」なのである。(中略)このような能力を持たない旧ソ連諸国は真の「主権国家」ではなく、したがって「上位の存在」であるロシアの影響下に置かれるのは当然だ、というのがロシアの論理であろう。この意味では、★安全保障を米国に依存する日本もまた、「主権国家」の定義からは漏れることになる。(中略)ロシア的用語法における「主権国家」(中略)とは、★「大国」に限りなく近い概念であると言えよう。》(P58、59、60) →★ロシアにおける日米関係への言説。沖縄への関心。
《(前略)ロシアが決定的に望ましくないと考える行動(NATOやEUへの加盟等)をロシアの介入によって果たせずにいる以上、消極的にはロシアの影響圏内に留まっていると考えることは可能である。現在のロシアが目指しているのは、まさにこのような意味での影響圏=★消極的影響圏を維持することであろう。》(P71、72) →★現在のウクライナ、ジョージアなど。
《こうした陰謀論的な世界観は、ロシアの政治的言説においては決して珍しいものではない。(中略)コロンビア大学のミッチェルが指摘するように、こうした★民主化革命を担った政治勢力への米国の支援は「重要だが小規模」なものであり、これらの運動が米国によって操られていたという性質のものではない。だが、ロシアにおいては「カラー革命」は米国によるロシアの勢力圏切り崩し工作とみなされた》(P74) →★マイダン革命におけるヌーランド氏を想起。
《ロシアの理解によれば、ロシアは、より弱体な国々の主権を制限しうる「主権国家」=大国であり、その★「歴史的主権」が及ぶ範囲は概ね旧ソ連の版図と重なる。その内部において、ロシアはエスニックなつながりを根拠とするR2P(保護する責任)を主張し、介入を正当化してきた。一方、ロシアの「歴史的主権」が及ばない旧ソ連圏外においては、ロシアはウェストファリア的な古典的国家主権の擁護者を以て自らを任じてきた。(中略)しかし、これは明らかな二重基準である。(中略)ロシアによる「歴史的主権」の行使も現在の秩序に照らして到底容認できるものではない。★ロシアに「歴史的主権」が認められるとすれば、論理的には他の大国もこうした特権を周辺諸国に対して持つことになるためである。》(P78、79)
《★★旧ソ連諸国は大国が取り合う駒ではなく、それぞれが主体性を持って戦略的に行動するプレイヤーである。ことに2010年代には旧ソ連諸国に対する中国の存在感が高まり、旧ソ連諸国はロシア、西側、中国という三つの勢力の間でマニューバー(域外大国を天秤にかける「コウモリ外交」)を行う余地を高めてきた。》(P80)
《ロシアが「歴史的主権」を守るために軍事力行使に踏み切ったグルジアおよびウクライナにおいては、NATOやEUへの加盟プロセスを凍結させるという効果をもたらす一方、★両国の反露的姿勢は一層確固たるものとなってきた。》(P80) →★「反露的姿勢」は今後変わらないと言い切れるだろうか。ロシアの揺さぶりは続き、変化もありうるのではないか。
◆第3章 「占領」の風景―グルジアとバルト三国
《2000年に成立したプーチン政権は当初、エリツィン政権末期に悪化した西側諸国との関係改善を掲げ、現在では考えがたいほど米国に配慮した外交政策をとった。(中略)だが、2000年代半ば以降、米露関係は次第に悪化の様相を辿るようになる。(中略)★旧ソ連諸国において相次いだ政変が米国の陰謀によるものであると見るロシアは、米国に対する不信感を募らせていった。》(P91、92)
《(前略)それだけに両「国家」(※アブハジアと南オセチア)の軍事力はロシアの強い影響下に置かれており、(中略)二つの未承認国家の実態が、ロシアによる「占領」であることは明らかであろう。》(P100、101)
《最近では、インターネット上のフェイクニュースも問題になっている。2014年のウクライナ危機において、ロシアはメディアやインターネットを総動員して「ロシアは介入していない」(中略)といった情報を広く拡散した。(中略)★「情報」が国家間関係においてこれまでにない力を持つ時代が訪れつつあると言えるだろう。》(P120)
◆第4章 ロシアの「勢力圏」とウクライナ危機
《ソ連崩壊後、★新生ウクライナはロシアの勢力圏からの脱出を目指したが、これは簡単なことではなかった。国際価格の数分の一という安価で供給されるロシア産天然ガスなくしては、ウクライナ経済は立ち行かないためである。自国を通過するロシアの天然ガス・パイプラインから多額の通行料収入を得てもいること、多くの工業製品や農産物がロシアに輸出されていること、ヒト・モノ・カネの往来が活発なことなどを考えても、ロシアとの関係を簡単に絶つわけにはいかなかった。》(P137)
《(前略)旧ソ連諸国向けのENP(※欧州近隣国政策)は東方パートナーシップ(EaP)と呼ばれ、2009年にスタートした。EaPの主眼は、旧ソ連諸国に民主化やガバナンスの改善といった国内改革を迫ることと引き換えに、「高度かつ包括的な自由貿易圏(DCFTA)」を結んでEUとの通商や人的往来を自由化するというものであった。(中略)しかし、DCFTAは参加国の経済政策を強く縛るものであるために、排他的な性格を有していた。(中略)これがロシアにとって極めて面白くないものであったことは明らかであろう。(中略)中でもロシアにとって受け入れがたかったのは、ウクライナのヤヌコーヴィチ政権までがEaPに基づくDCFTAへの参加の意向を示したことであった。》(P143、144)
《(前略)クリミア半島の併合はロシアの介入においてもかなり例外的なケースである。★紛争地域をそのままロシア領に組み込んでしまったという例は、ソ連崩壊後ではクリミアだけであるためだ(ソ連時代まで含めても前述したバルト三国の再併合まで遡る)。他方、★旧ソ連における紛争でよく見られるのは、分離独立勢力が法的親国との紛争の末に未承認国家を形成し、ロシアがこれに経済援助や軍事プレゼンスを提供するというパターンである。そして、ロシアの後ろ盾を得た未承認国家を法的親国が排除することはまず困難であり、分離独立状態は膠着化して、いわゆる「凍結された紛争」となる。(中略)ドンバス地方での紛争は、より伝統的なロシアの介入パターンに近い。》(P161)
《(前略)ロシアとの終わらない紛争を抱えているということは、当面はNATO加盟が不可能になることを意味している…。(中略)★戦争状況を継続させることそのものがロシアの目標であると考えられよう。》(P165)
《(前略)比較対象を旧ソ連諸国にしてみると、今度はロシアの圧倒的な軍事的優位が際立つようになる。(中略)★ロシアは旧ソ連諸国内で最大の兵力と唯一の核戦力を保有しており、他の追随を許さない。(中略)さらに★ロシアは民兵などの非正規軍事力を大量に動員する能力を有しており、★最近ではここに民間軍事会社(PMC)が加わるようになった。》(P170)
《ロシアにとって重要なのは、旧ソ連諸国に対して介入を行う際、★西側がそこに横槍を入れてこないよう抑止しておくことである…。(中略)ロシアの振る舞いを西側が軍事力で阻止しようとするならば、ロシアは通常戦力によってその抑止を試みるし、★抑止が破れれば核兵器を使用する(あるいはその脅しをかける)ことで介入を思いとどまらせようということだ。》(P170、171) →★ウクライナ危機と核兵器。ロシアは西側の介入を阻止する「切り札」としてアピール。また、核を放棄した国ウクライナにとっては国際約束を破られ、他国(北朝鮮やイラン)への影響も懸念される。
◆第5章 砂漠の赤い星―中東におけるロシアの復活
《シリアへの介入によってロシアが中東における影響力を著しく高めたことは事実であるとしても、この地域においてロシアが米国に代わる存在となったと見るのは過大評価であろう。★旧ソ連の勢力圏から遠く離れた地域においてロシアが発揮できる秩序維持能力は著しく制約されたものであるためだ。(中略)経済的にも、ロシアが大規模な軍事プレゼンスを展開しうる余地は小さい。(中略)国民感情の面からも同様である。》(P178、179)
《ロシアがシリアに対する介入で一定の成果を上げられた要因はいくつか挙げられる。たとえば、シリアでの空爆においてロシア航空宇宙軍が無差別爆撃を多用していることはその一つである。(中略)★シリアにおけるロシアの「戦果」は、民間人の巻き添え被害を厭わない根こそぎ型の爆撃に支えられている部分が大きいと言える。》(P181)
《ゲラシモフ参謀総長が述べているのは、シリアのような遠隔地への介入に際してはロシアがすべてを丸抱えしないという方針である。★ロシアが担うのは、介入の中核となる軍事力(たとえば空軍力や特殊部隊等)とその運用の基礎となる情報収集・指揮統制等を提供することであり、介入の実際は「関連国家の軍事編成、各派の軍事機構」と連携して行う。(中略)ロシアはシリアにおいて民間軍事会社(PMC)も活用している。中でも有名なのが「ワグネル」だ。》(P184、186)
《ごく単純化して言えば、西欧諸国の中東に対する関心は、主として植民地時代の利権維持と地理的に近接しているがゆえの脅威(宗教過激派によるテロや移民の大量流入)の封じ込めが主たる動機であると考えられよう。米国の場合、これは石油を中心とするエネルギー資源の安定供給とこれを脅かす敵対的勢力の排除と理解できる。しかし、ソ連やロシアにとっての中東の位置づけはこれと大きく異なる。(中略)★ロシアの対中東アプローチは、個々の状況に応じた(transactional)非イデオロギー的・即物的なものであり、しかも個々の国・アクターとの二者間関係が中心である。そこには★長期的な「中東戦略」のようなものは見られない。(中略)あらゆるアクターと一定の対話チャンネルを有することは、ロシアが仲介者あるいはバランサーとして振る舞いうることを意味する。》(P189、190、191)
《ロシアは中東における米国の影響力低下を巧みに利用し、自国に利用可能な政治的・経済的・軍事的資源の範囲内でその影響力を大きく高めた。さらにロシアはシリアにおける海空軍拠点を21世紀半ばまで維持するとの合意をアサド政権ととり付けており、エジプトやリビアでも軍事拠点の獲得を目指していると見られる。(中略)ロシアの軍事的関与は各種の制約から限定的なもの(「限定行動戦略」)とならざるを得ず、それゆえに★介入先の現地諸勢力との関係が決定的な重要性を持つ。特に注目されるのが、イランとの関係だ。》(P195、196)
《ロシアは中東への影響力を回復する途上にあるものの、その度合いは★あくまでも域外大国としてのそれに留まると考えられよう。》(P198)→★ロシアのアフリカ大陸への関与も同様、もしくはより利益中心主義的ではないか。
◆第6章 北方領土をめぐる日米中露の四角形
《これらの★北方領土駐留部隊は(中略)クリル諸島(北方領土と千島列島を併せたロシア側の地理的概念)の内側に広がるオホーツク海の防衛である。オホーツク海はカムチャッカ版図に配備された弾道ミサイル原潜(SSBN)のパトロール海域とされており、北極海をパトロール海域とする北方艦隊のSSBN艦隊と並んで★ロシアの核抑止力(特に第二撃能力)を担う。(中略)★北方領土は核抑止という最上位の軍事戦略と密接な関連性を有する地域であり(後略)》(P214、217)
《ロシアの中国観もこれと同じだという。巨大な力を持つ隣人とどう波風を立てずに付き合っていくか、言い換えれば、★隣人をいかに隣人のままに留め、敵にしないかがロシア極東部の関心なのだ。(中略)このような傾向は、極東に限らず、ロシアの対中政策全体にも見て取れる。ことに2014年のウクライナ危機以降はそれが顕著になった。(中略)ロシアの対中安全保障政策は「同盟にはなれないが敵にもならない」という関係の構築を目指して進められてきた。》(P230、231、234)
《巨大な隣人と直接に国境を接している★ロシアの対中脅威認識は日本などの比ではなく、それゆえに中国との関係悪化をなんとしても避けることこそがロシアにとっての安全保障とみなされている、という構図が描けよう。》(P235)
◆第7章 新たな地政的正面 北極
《ロシアは北極に大きな経済的意義を認める一方で、その裏返しとして軍事的な脅威認識を強めるというアンビバレントな様相を呈している。それゆえに、国家として見た場合のロシアの北極政策には、協調的な側面と対立的な側面の双方が混在しており、周辺諸国にとっての不確定要素とみなされてきた。》(P258)
◆おわりに 巨人の見る夢
《ロシアを夢見る巨人と見立ててもよいかもしれない。ユーラシアの巨大な陸塊の上で、ロシアは壮大な「勢力圏」の夢を見ている。(中略)寝返りを打てば、隣人たちに影響を与えずにはいられない。》(P262) →★イメージとしては、切断された腕を近くし続ける巨人かもしれない。幻の腕。しかし、骨は断たれても神経は一部つながっている…。ソ連崩壊は終わっていない。
【コメント】
★1章=北方領土問題も「貴重なアイデンティティ」と直結している。サハリンでの戦勝記念パレードを想起。
★2章=「反露的姿勢」は今後変わらないと言い切れるだろうか。ロシアの揺さぶりは続き、変化もありうるのではないか。
★4章=ウクライナ危機と核兵器。ロシアは西側の介入を阻止する「切り札」としてアピール。また、核を放棄した国ウクライナにとっては国際約束を破られ、他国(北朝鮮やイラン)への影響も懸念される。
★5章=★ロシアのアフリカ大陸への関与も中東同様、もしくはより利益中心主義的ではないか。
★おわりに=イメージとしては、切断された腕を近くし続ける巨人かもしれない。幻の腕。しかし、骨は断たれても神経は一部つながっている…。ソ連崩壊は終わっていない。
▽「地政学」なのでロシアの内政的要素にはほとんど触れていない。
▽「浸透膜」の両側を行き来しての経験。